加熱するふるさと納税の返礼品に総務省がクサビを打ち込む通達を出したのが今年の4月1日。
4月1日付でお礼の品を見直す自治体もある中で、モンベルのポイントバウチャーやコールマンのオンラインポイントを返礼品とする長野県小谷村などは返礼率50%のまま粘ってきましたが、いよいよ粘り切れなくなったようで7月1日から返礼率の引き下げに動くことになったようです。
ランキングに参加してみました~♪
ポチってしていただけると更新の励みになります( *´艸`)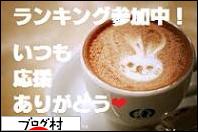
お礼の品の返礼率の引き下げに総務省が躍起な理由
そもそも、どうして市町村のふるさと納税の返礼率合戦に総務省が待ったをかけるのでしょうか?
ふるさと納税は地方税である県民税や市町村民税を移転する制度なので、国税を管理している総務省が口を挟むのは些か不条理な気がしていましたが、ちょっと調べてみるとそりゃ~総務省は嫌だよねと納得できました。
モデルケースを作って考えてみた
X県Y市に住むAさんが、Z市に10,000円ふるさと納税し、5,000円のお礼の品を受け取った、という簡単なモデルケースで考えてみました。
計算が複雑になって趣旨から外れていきますので、お礼の品を用意した会社などのことは除外しています。
ふるさと納税したAさんの収支
Aさんは10,000円の持ち出しとなりますが、X県とY市への住民税(県民税と市民税)の支払いが8,000円減り、自己負担は2,000円となります。
さらに5,000円のお礼の品をもらえますので、考えようによっては差し引き+3,000円になります。
ふるさと納税を受け取ったY市の収支
Z市は10,000円の増収となりますが、お礼の品に5,000円支出します。
差し引き5,000円の増収になります。
Aさんが住んでいたX県とY市の収支
県民税と市民税合わせて8,000円が減収となります。
ただし、ふるさと納税では減収分の75%を地方交付税として受け取ることができます。
このため、国から6,000円が補助され、差し引き2,000円の減収に留まります。
国の収支
X県とY市の減収分を補うため、6,000円の持ち出しになります。
結果として国が一人負けする制度だった
簡単なモデルケースにしましたが、結果としてふるさと納税を受けたZ氏が最も増収となり、次いでAさん、X県とY市は微減で国が大きく持ちだす、国が一人負けする制度になっているようです。
ふるさと納税は税収の地方格差を無くすための制度であったので、基本的に市町村が魅力的なお礼の品でふるさと納税を誘導すること自体は間違ったことではないと考えます(残る額の如何を問わず、増収となることには間違いない)。
正直なところ「もうこれ以上ふるさと納税で交付税の使い道を絞められたくない」という総務省の願いをそのまま言うわけにもいかず「ふるさと納税でお礼の品合戦が行き過ぎている」という理由にすり替えているんじゃないのかな?
なんて、調べていて感じました。
こんな風に思うのって穿った見方なのかな・・・?